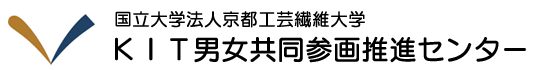両立支援ガイドブック
仕事と育児・介護の両立に関する学内制度や支援情報をわかりやすく1冊にまとめました。
仕事と育児・介護の両立支援ガイドブック<改訂第2版>(令和6年2月発行)
(PDF 3.95MB)
カテゴリごとのファイルをご希望の場合は、下記をご利用ください。
- 表紙、目次 ~ 妊娠・出産・育児期(PDF 2.7MB)
- 介護期・両立支援制度 ~ センター紹介、学内問合せ先(PDF 1.51MB)
- ※制度の最新情報については直接各担当窓口へお問い合わせください。
<これまでの発行物>
仕事と育児・介護の両立支援ガイドブック<改訂版>(令和3年4月発行)
(PDF 8.75MB)
カテゴリごとのファイルをご希望の場合は、下記をご利用ください。
仕事と育児・介護の両立支援ガイドブック<改訂版>(平成29年10月発行)
(PDF 8.75MB)
カテゴリごとのファイルをご希望の場合は、下記をご利用ください。
WLB(ワークライフバランス)ミニ講座
仕事と生活の両立(ワークライフバランス・WLB)を考える上で必要な子育てや介護、女性のヘルスケアに関するミニ講座を開催しました。
WLBミニ講座2014「女性の健康-変化とケア」
日 時:平成26年8月25日(月)14時~15時
講 師:松岡 知子 氏(京都府立医科大学医学部看護学科 教授)
女性は生涯を通して女性ホルモンの影響を大きく受け、月経、妊娠、出産、閉経、高齢期へと変化していきます。WLBを考える上で大切な女性特有の健康状態やケアについて、お話を伺いました。
- 女性ホルモン(エストロゲン)量の変化
・40歳以降(更年期)、女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少により、自律神経が乱れ様々な不調が
あらわれる
- 40歳代に起こりやすい月経不順から閉経までのパターン
・正常な月経周期が短くなってくる
・一部が無排卵月経に
・2~3ヶ月に一度の希発月経に
・閉経(月経が1年以上ない状態)
- 更年期障害の主な症状
・のぼせ、冷え症、ほてり、めまい、むくみ、頭痛、腰痛、肩こり、不眠、疲労倦怠感など
・閉経女性の40~80%に認められ、1~数年間続き、長期にわたる場合も
- 更年期障害が起こったらどうする?
・病院を受診
更年期障害で見られる症状は、他の病気が原因で起こる症状に似ていることもあるため、すべてを
「更年期障害のせい」と思いこむことがないよう注意が必要
・セルフケア
症状が軽く、食事や運動、リフレッシュなど日常生活の工夫で乗り切れる場合はセルフケアで様子
を見る
- ホルモン補充療法の主な効果と副作用
・ホルモン補充療法(HRT)は、欠乏しているエストロゲンを補う療法
・からだ全体に良い効果をもたらし、のぼせ、ほてり、発汗などの症状を改善
・骨がとけだすのを抑え、骨量を維持し、骨粗鬆症を防ぐ
・意欲や集中力の低下を回復させ、気分の落ち込みを和らげるなど
・月経用の出血、筋腫が大きくなる、子宮癌との関係、胃の不調、乳房の張り、乳癌になりやすくなる、
などの副作用がみられる
・ホルモン薬を使用する方は、毎年の乳癌・子宮癌・卵巣癌検診が必要
- 漢方薬
・薬物療法と比べて副作用が少なく、長期的使用が可能
・個人の体質によって薬の使い分け
更年期障害に代表的な漢方薬・生薬
当帰芍薬散―めまい、動悸、頭痛、手足の冷えなど
桂枝茯苓丸―のぼせ、ホットフラッシュなど
加味逍遥散―精神不安、不眠、イライラなど
・ホルモン薬と比べて効果がでるまでに時間がかかり、人によって効果がでないことも
- サプリメント
・更年期障害を軽減するひとつの方法。過剰摂取を防ぎ、自分の体質に合うものを選ぶ
・ローヤルゼリーには、自律神経の乱れを整える効果と女性ホルモンの分泌を促す効果がある
・ビタミンB6、ナイアシン、ビタミンE、パントテン酸、アセチルコリン、マンガン、コエンザイム
Q10なども更年期障害を和らげる
- 運動の効果
・生活習慣病の予防、アンチエイジング効果、ストレス解消、持久力や疲労回復力の増進などにより、
更年期障害を軽減する
・有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・水泳・ヨガなど)、ストレッチ、マッサージ、筋トレなど
が効果的
・速足、階段、家事など身近にできる軽い運動を長く続ける
- 睡眠の効果
・十分な睡眠は健康にとって必要不可欠。規則正しい睡眠は心身の疲れを取り、パワーを回復させ、
更年期障害を軽減する
- 更年期の食生活
・カルシウムや食物繊維を多く取り、コレステロール、塩分を控えるなど食生活を見直し、バランス
の良い食事を心がける
- 心のバランスを整えるヒント
・気分転換を心がける
・深呼吸をする
・趣味やレジャーを楽しむ
・飲酒や喫煙、早食い、大食いなどに注意
・ストレスを溜めない
・リラックスする時間を作る
・自分のための時間を作る
・笑うこと、話すこと、楽しむことを日々忘れず、新しい人との交流や異性への関心を持つ
・一人で悩まずにパートナー、家族、友人など周りの人に援助を求める
(講座資料より抜粋)